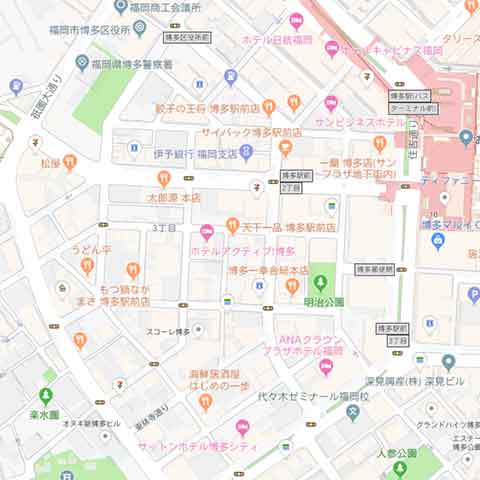客は元々、少なかったわけだから、それだけが理由とはいえない。
だが、もっと繁盛していたらこのような事態を招くことにはならなかったことは明らかなことでもある。
出入りする客の総数が極端に減ったのではなく、卓の立つ回数が少なくなった。
なぜそうなったのか。
原因を今さら探ることは不毛なことだと思えるし、果たして自分がその立場に、勝本さん(仮名)のようにクラブを経営する立場に立っていたら彼とは違う手段を講じたかもしれないが、そのようなことを考えることそれさえも、あまり意味の無いことのように思える。
私が人生の中でもっとも多くの場代を貢いできたクラブ「Y」は、創業28年目の秋に営業を停止した。
ぶらりとテッポウで顔を出し、何の気兼ねもなく卓に付けるクラブの一つが潰れた。
終焉の始まりは、いつだったのだろう。
最強のメンバー、甲賀さん(仮名)が辞めさせられたのは、2年近くも前のことだが、このことと無関係ではないような気がする。甲賀さんはあんなに麻雀が強く、勝ち続けていたにも関わらず、多くの常連客から好意を寄せられていた。
身体障害者手帳を持っていた甲賀さんは、見た目は健常者とちっとも変わらないが、3日に一度は人工透析を受けなければいけない体で、たった二人しかいないメンバーの一人が半日も病院に拘束される曜日の営業はありえなかったために、クラブ「Y」は週にたった4日しか開店しない、限られた常連客だけのメンバー制雀荘として細々と成り立っていた。
ある夜、マダムが若いツバメを伴って、クラブ「Y」を訪れた。
マダムは昔からの勝本さんの知り合いで、市街地の大きなフリー雀荘のオーナーでもある。60歳をとうに超えた彼女が連れていたのが、その雀荘のメンバーでもある海堂君(仮名)で、私より幾らか若い彼は、それから一週間も経たずに独りで「Y」に打ちに来るようになり、そのマダムが店を閉めてからは、半分メンバー半分フリー客みたいな存在になり、他の仕事が見つかるまで、みたいな契約で、自然と「Y」のアルバイトメンバーになった。
海堂君は健常者であり、既にメンバー経験者でもあるので、メンバーとしての接客業務や様々な雑事は充分こなすわけで、実際に囲むことの多い甲賀さんよりも、勝本さんの立場からするとずっと重宝するのは当然のことだった。
開店している日であっても客が独りも来ないことがあるクラブに三人の従業員は無理な話。
甲賀さんの居る場所がなくなってしまった。
常連客の誰もすぐにそうとは気づかないうちに、甲賀さんはクラブを辞めた。
海堂君は着実に仕事をこなし、常連客ばかりの中にかなりスムースに溶け込んでいったので彼の所為ではないが、甲賀さんがいなくなったことで、二人の常連客の足が遠のくことになった。
二人は昔からの「Y」の客である以前から、甲賀さんとは付き合いがあり、わざわざ「Y」に顔を出す特別な理由をなくしただけのことだ。
たった二人がいなくなるだけでも、トータルで卓の立つ回数が減ったかもしれない。少なくとも半荘の行なわれる回数は間違いなく少なくなったはずだ。
毎月の売上を締める勝本さんはあせった。私にも様々な相談が持ちかけられた。
新規の客を増やすにはどうしたらいいか。懐に余裕のある客に長く遊んでもらうためにできることは何か。セット客を確保するために流行りのクラブはどんな広告を打っているのか。
できることもたくさんあったが、実際に勝本さんがそうしたことのために何らかの手段を講じることはなかった。
卓が立つ回数が少なくなると、場代が上がらない。
家賃や自動卓のリース料、光熱費が払えない状態となった。
常連客の中でも素性のはっきりとした何人かの人間に、共同経営者にならないかとの相談を勝本さんは持ちかけた。私も声を掛けられたが、他の常連客同様にその話を断った理由は、私にとって「Y」は遊ぶ場所だったし、共同経営者になるために準備しなければならない金銭的な余裕もなかったからだ。
常連客の誰も話には乗ってこなかったが、半年くらい前から顔を出し始めた客の独り、屋内電気設備の工事請負を生業とする職人の親方が幾らかの金銭を融通することでその場をしのぐことができた。
親方は、それまで薄汚れていた店内を清掃し、普通のクラブにあって「Y」にはなかった設備(電子レンジや服掛けハンガーやちょっとした荷物の置き場所や飲み物以外も入れておける冷蔵庫など)を準備し、新しい何人かの客を連れてきた。メンバーは二人いるので親方自らがメンバー仕事を行なうことはなかったが、客が独りでもいれば自分も卓に付いて、卓を継続させる努力をおこなった。一卓でもいいから常に卓を立てておくこと、私がアドバイスした売り上げ確保のための一つの方策だ。
こんな風にしてクラブが生まれ変わることもあるのか、私は親方の奮闘ぶりを認めながらそう思っていたが、それから半年もしない内に事件は起こった。
親方には表家業で膨大な借金があり、それは麻雀クラブの売り上げで担保できる程度の額でなく、勝本さんも署名させられていた借金を残したまま行方をくらましたのだ。
勝本さんと海堂君の二人ならば以前のように、週に四日だけの営業、である理由は何もない。日曜日以外は毎日、「Y」は開店することになった(実際に客が訪れるか、卓が立つ立たないにかかわらず)。
そして、海堂君が負けだした。
と言うより、余裕の無い毎日の中で、少ない客を相手にしての麻雀(それもほぼ常に入っていなければならない麻雀)で勝ちを維持し続けることは困難なことで、ましてこのクラブの客は皆、総じてカタい腕を持っている。麻雀クラブで働いて得ることのできる収入だけで、毎日、麻雀を打ちながら暮らしの生計を立てることなどできる筈もないのだ。
客ではないので、どんなに負けてもその卓から抜け出すことはできない。たまに大きく勝つと、客の方が卓を離れてしまう。
海堂君の負けが実際にどれくらいのものだったのか、私は知らされていないが、まっとうに働いて返金するのが馬鹿らしくなってしまう額になっただろうことは容易に推測できる。
彼の挙動がおかしくなった。
営業時間内に彼あてに意味不明の電話がしょっちゅう掛かってくるようになった。
私にはスグにそうとしれた。それは借金返済を求める電話なのだった。
やがて、海堂君はクラブを辞めた。
海堂君を催促する電話は、彼がクラブを辞めた後も毎日、続いた。
この店の電話機は昔ながらのピンク電話がカウンタに一台あるだけで、メンバーが卓に付いている時には卓から離れて電話機の傍まで行かなければならないという前時代の遺物なのだが、昨今は客の全員が携帯電話を持っているのでさしたる不都合はなく、この電話は常連客が、卓が立ちそうなのかどうかを勝本さんに確認するためだけに使用されていた(勝本さんは携帯電話を持っていない)。
海堂君がこのクラブを辞めたことを何度告げても、その相手は毎日、それも約10分ごとに催促の電話を入れてきた。
その相手は東京の業者で、このクラブの電話以外に海堂君へのアプローチの道を持っていないと知れた。そして海堂君が居留守を決め込んでいると疑っているか、唯一の連絡先であるこのクラブに嫌がらせをすることで、彼との連絡が付く可能性を求めているのかもしれない。
毎日、何度も何度も、電話が鳴るのである。
客からの連絡かもしれないので出ないわけにはいかない。ひどい時には、5分ごとに業者からの電話が入った。メンバーは卓に付いている勝本さんだけの状態に、である。
その度に局は中断し、ようやく立った卓であるのに、麻雀どころではなくなってしまった。
資金繰りの問題はまったく解決されないままだったが、常連の中で唯一の筋モノである高山氏(仮名)が共同経営者となることになった。
昔から客の中には何人かの組織人がいたが、今では高山氏だけが残った形で、彼はただ麻雀を楽しみにその「Y」に顔を出しているだけだ。
高山氏の出身地は、私が若い頃、無茶を送っていた時代に遊んでいたクラブの近所で、博多でも当時元気の良かったいくつかの組織の重鎮達が毎晩大きな額の金銭をやり取りしていた賭場に出入りしていたせいで、何人もの共通の知人(?)の名前があったが、彼は博徒としては古いタイプの人で、オイチョカブやメクラ専門であり、麻雀はそのクラブでは負けることの方が多かったはずだ。
私と一緒に囲むのを極端に嫌っていたが(私は何故か高山氏と囲むと好調だった)、自分が経営者となってからは嫌がってはいられない。卓が立たないよりはマシだと思っているだろう。私とも何度も囲んだ。私は総じて勝ちつづけた。
海堂君あての電話は相変わらず鳴りっ放しで、店の経営者が二人とも入っての卓で、客である人間が勝つことの方が多い状況で、日々は過ぎていった。
高山氏が声を荒げた。
いつもより多く集まった常連客の対応の中で、毎日の電話にネを上げた形だ。
「おい、いつでも出てこい。俺は**会**組の高山だ。逃げも隠れもしないから」
上の言い回しは不正確だが、本物の啖呵の切れ味は、私がこれまでに見たどの東映やくざ映画よりもカッコ良かった。
普段はそんな態度はおくびにも出さない高山氏の声を初めて聞いた、その日、何人かいた客は、その日を境にクラブから足が遠のく結果になった。
高山氏は負けが込むと平気で店の金庫から売り上げを支払いに充てた。
勝本さんは高山氏の所業を横目で見ながら、何も言うことができなかった。
ここまでかな。
私にも理解できた。このクラブはもう限界なのだ。
勝本さんから無心の願いが、私の携帯に入った。
それは断ることのできない金額だった。
「クラブは手放す。次の職場も見つけたから。落ち着いたらキチンと連絡するから」
勝本さんの声は情けないほど、か細いもので、私は悲しくなった。
返すのはいつでもいいから、連絡だけはくれるようにとの念を押して私は指定された口座に金額を振り込んだ。
誰か独りのせいではない。
いくつかの不運が重なったのは事実だが、そうしたことを招いた根本的な原因はどこかにあるのだろうとも思える。
私がもっとも多くの場代を使ってきた、気のおけないクラブが無くなったことで、それから数か月の間、別の雀荘へも出かけなかった。
今にして理解った。私にとってのホームグラウンドだったのだ。
「Y」でだけ一緒に顔を合わせた何人かの打ち手と、これから先にどこかの雀荘でまた出会うことがあるのだろうか。
今の私に知る由も無い。