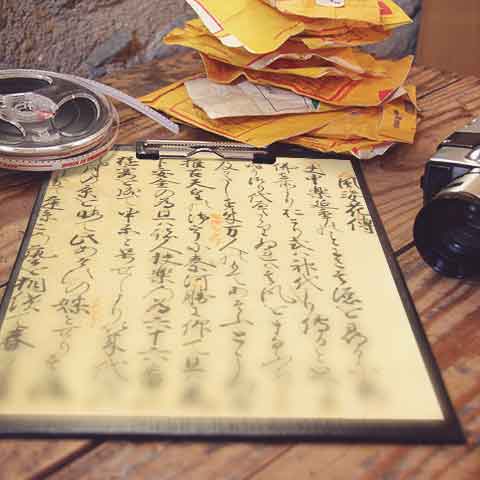問う。これに大いなる不審あり。
はや劫入りたり仕手の、しかも名人なるに、ただ今の若仕手の立合いに勝つ事あり。これ不審なり。答う。これこそ、先に申しつる、三十以前の時分の花なれ。
古き仕手は、はや花失せて、古様なる時分に、珍しき花にて勝つ事あり。
真実の目利きは見分くべし。さあらば、目利き、目利かずの、批判の勝負になるべきか。
質問。
麻雀の競演において、今ひとつ大きな疑問があります。
それは、かなり年期も積んだベテランの打ち手で世間でも名手名人と言われているのに、まだ駆け出しの若い打ち手に負けることがありますが、これはどういうわけでしょうか。
答え。
これこそ、先に申した、三十歳以前の一時的な若さによる花の強さである。
年輩の打ち手で、もはや花が失せ、ヒキが弱くなった打ち手に、鬼ヅモを繰り返す若い打ち手が勝つことはそう珍しいことではない。
本当の麻雀観戦者はこのあたりのことを見分けるものである。
目が利くか利かぬか、この違いを見分けるのも批評家の眼力というものである。
この問答は、年若い打ち手である世阿弥が、やや年老いた父親、観阿弥に尋ねているいるだけになかなかの迫力がある。
それというのも当時、既に若い打ち手の中でもスターであった世阿弥が、年老いた観阿弥よりも、麻雀の地力において絶対的な自信があれば、このような質問はできなかったろうと思われるからだ。
言い換えると、若い、昇り調子のスターとはいえ、父の観阿弥には到底まだまだ麻雀の本質的な部分では勝てない、という自覚があったからこそ、このような率直な質問をすることができたのだろう。
さりながら様あり。
五十以来まで花の失せざらん程の仕手には、いかな若き花なりとも勝つことはあるまじ。
ただこれ、よき程の上手の花失せたるゆえに、負くることあり。いかなる名木なりとも、花の咲かぬ時の木を見ん。 犬桜の一重なるとも初花の色々と咲けるを見ん。
か様のたとえを思う時は、一旦の花なりとも立合いに勝つは理なり。
若さが勝つ、と言ってもこれにも問題はある。
五十歳(この年令は、充分に年期を積んだという以上に特別な意味はない)を過ぎても花のなくならない、優れた打ち手との勝負にあっては、どんなにヒキの強い、若い打ち手であっても簡単に勝てるものではない。
ベテランの打ち手が、若い打ち手に負けることがあるのは、はっきり言うと、相当程度にうまいとはいえ、その実、ヒキが弱くなったからである。
それは、どんなに評判の良い花の咲く木であっても、実際に花が咲かなくなったら、誰がそんな木を鑑賞するものか。
つまらぬ一重桜であっても、咲き始めた花が美しければそちらを愛でるのは当然である。
このように考えると、一時的な花でも実際の半荘で、年老いたベテランの打ち手に勝つのはむしろ当然というものだ。
ここでも花という言葉が繰り返されている。
観阿弥が言っている花は、ヒキの強さという言葉に置き換えられるが、本来は卓を囲んでいて、その自然な動作からかもし出される打ち手の「華やかさ」と「艶やかさ」のことであった。
打ち手から発散されるオーラというか、他の三人を圧倒する迫力のことでもある。
この花は、生来の資質とふだんの修練によって培われるものだが、それに加えて、その打ち手の、勝負に対する前向きの気迫のようなものも欠かせない。
嵌張待ちであっても、地獄待ちであっても、それを自分でツモるぞ、というような時の気迫である。
こうして得られた本物の花(=ヒキの強さ)であれば、ただ若いだけの、無謀さともいえる盛りの花がそんなに簡単に勝てるものではない、というのである。
むろん、こう言い切る背景には、自分は年老いてはいるが、簡単に若い打ち手には負けない、という観阿弥の誇りと自信とが見える。
しかし、すべてが観阿弥のように力量がある者ばかりではない。
一時期、名人上手などと言われても、年令とともに精気を失い、花の艶やかさの薄れた麻雀打ちもいる。
それはちょうど、昔、美しい花を咲かせると言われて、今はほとんど花を咲かせることのなくなった老木に等しい(これまで使っていた「花」という言葉を、実際の植物の花を例えにしての、逆転的な言葉の使い方が面白い)。
そんなものより、今現在、たしかに初々しい花を咲かせている木の方に人気が集まるのは当然である、と言い切っている。
この残酷なまでの比較のなかに、過去の名声や昔取ったタイトルのことなどは無意味だとする、観阿弥の潔さがよく表れている。
そしてこのことはまた、麻雀界におけるファンの目移りの冷淡さや、メディアでの扱われ方を熟知したうえでの厳しさでもある。
いずれにせよ、以前はどうこう言ったところで、重要なのは今、どのような花を咲かせているか、という事実である。
そこまで見据えていたからこそ、老いてなお花のあった観阿弥の麻雀が成り立っていたのである。
されば肝要、この道はただ花の命なるを、花の失するをも知らず、
もとの名望ばかりをたのまんこと、古き仕手の返す返す誤りなり。
かくして最も重要なことは、この麻雀の道は、ただ花のあることがその本質であるのに、もはや花が失せたのにも気付かず、かつての名声や古臭い麻雀理論、確率などというものだけに頼っているのは、ベテランの打ち手がよく犯している大きな誤りである。
観阿弥の冷めた厳しい目はここにきわまる。
花が命であるのに、その花を失い、過去の名声や確率論などという小手先の技だけにしがみつく姿は、現代のさまざまな世界のいわゆる老害という言葉にも通じてくる。
実際、企業や組織の中にも、何の名案も行動力もなく、役職の椅子に居座っている老いた社長や役員は多そうだ。
それを思うと、六百年の歳月を超えて現代にも通じる「見事な喝破」と言えるかも知れない。
物数をば似せたりとも、花のある様を知らざらんは、花咲かぬ時の草木を集めて見んが如し。
万木千草において花の色も皆々異なれども、面白しと見る心は同じ花なり。
物数は少なくとも一向の花を取り極めたらん仕手は、一体の名望は久しかるべし。
されば主の心には、随分花ありと思えども、人の目に見ゆる公案なからんは、田舎の花、薮梅などのいたずらに咲き匂わんが如し。
理論理屈の数だけやたらたくさん学んでも、ヒキの強さとは何かということを知らぬ打ち手は、あたかも花の咲かない草木だけを集めて見ているようなものである。
この世にたくさんある木や草の花々は、その色合いや形こそ違っても、咲いている花を素敵だと眺める人々の気持ちは全員同じであって、それが美しいからにほかならない。
自分で構築し、学んだ理論や理屈が少なくとも、ある一面の花(ヒキの強さ)をとことん極めたような打ち手であれば、「あの打ち手は、ある局面では間違いなく強い」というような評価は長くされるものだ。
以上のようなわけだから、打ち手本人がどんなに「自分は色んな場面でのヒキが強い」と思い込んでいても、その花を観客に理解させるような工夫がなければ、田舎の花や薮の中の梅のように、見る人もなく無駄に咲いているのと同じである。
ここまでくると、観阿弥の、麻雀打ちとはどうあるべきかという問いに対する考えがよく見えてくる。
理論理屈、確率重視のデジタル麻雀でなく、ここ一発という時のヒキの強さこそを重視しているのである。
多くの理論理屈を身に付けていてもあまり意味がないだけでなく、たとえたまたまある局面においてヒキが強かったとしても、それを観戦しているギャラリーにもよく理解させるような工夫がなければ、真の麻雀打ちとは言えないとまで考えていたことがわかる。
このことはまた、一般庶民の目をいかに重視していたかの表れで、ともすれば「俺の麻雀を判らぬ者は低劣だ」と一般麻雀ファンを軽視する高踏的な立場にいるプロ雀士やアーチストへの痛烈な一撃といってもいいだろう。
また、同じ上手なりとも、その中にて重々あるべし。
たとい随分極めたる上手、名人なりとも、この花の公案なからん仕手は上手にては通るとも、花は後まではあるまじきなり。公案を極めたらん仕手は、たとえ技は下がるとも花は残るべし。
花だに残らば面白き所は一期あるべし。
されば、真の花の残りたる仕手には、いかなる若き仕手なりとも勝つことはあるまじきなり。
たとえ、同じ上手といっても、その上手の中にも色んな段階がある。
多くの理論理屈を極めた打ち手であっても、ヒキの強さについての工夫がなければ、世間一般には一応、上手として通用したとしても、長い期間、その花が残ることはないだろう。
ところが、ヒキの強さについて工夫し、それを第一に考えている打ち手であれば、たとえ年令のせいで肉体的に衰えてきて瞬時の判断で迷うような事態になって、麻雀の技が下がってきたとしても、ヒキの強さは残るものだ。
ヒキの強ささえ残っていれば、その麻雀打ちにとっての打ち手としての魅力は、生涯消えぬものである。
このような次第だから、真の麻雀の花の残っている打ち手には、どんなに威勢の良い若い打ち手であっても、容易に勝てるものではないのである。
ここで、観阿弥の麻雀に対する結論が示される。
要するに、なまじっかな理論や理屈の数よりも、その打ち手が持っているヒキの強さこそが本当に大事なことなのだ。
花があれば腕も長持ちするし、どんなに若い花がぶつかってこようと簡単に負けることはない、と。
こう言い切る観阿弥には圧倒的なヒキの強さがあったし、また自分でも誰にも負けぬ花があることを確信してもいた。
事実、この問答を繰り返していた時も、若きスターである息子の世阿弥に劣るなどとは思っていなかったのだろう。
しかし、こと麻雀において、その圧倒的な自信、確信を持ち続けていられたその感性こそは、ともすれば独善的で過信に満ちた驕りに聞こえるかもしれない。
それを乗り越えた者だけが言い切ることができる数多くの言質と、それを素直に受け止めていた若きスター世阿弥の麻雀に対する真摯な姿勢が、六百年という歳月を超えてなお、この問答集が我々多くの麻雀愛好家に受け入れられている所以でもある。
そんなバカな…。