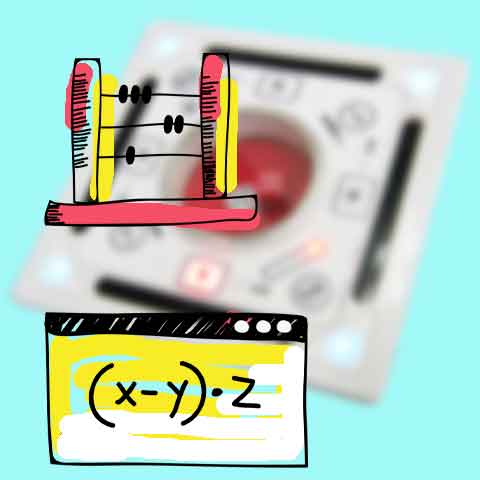彼は元々デザイナー志望の学生だった。
何となく選んで入った美大の雰囲気に馴染めず、半年で中退することを決め(授業料は一年間分前納していた)、生まれた里に戻って家具工場に就職した。
彼の地元は古くから家具の産地として全国的に知られた土地で、彼が入った工場は中学校の先輩にあたる(とはいうものの面識はなかった)彼とはいくつも歳の違わない若い社長が設立したばかりの小さなものだった。
仕事そのものが面白いとは思わなかったが、これから工場を大きくしていこうという社長の考えには共感できたし、働いている全員が若い、活気にあふれた職場だった。
ところが、彼が入社して一年も経たずに工場の経営は破たんし、その工場は社員まるごと大きなメーカーに買収されることになった。
進退も含めた相談をするメーカーの人事部との面接で、彼は開発企画部への配属を望んだがそれはかなえられなかった。
だが、彼はその工場に残ることにした。
独学で工業デザインの基礎を身に付けた。
そしてすぐにチャンスは訪れた。
新時代に提案すべきオフィス製品に関する社内アンケートで、彼は自分のデザインしたオフィス机と書類ロッカーについての企画書を勝手に添付したのだ。
それが開発企画部の部長の目に止まり、彼の本社勤務の夢はかなえられた。
モノの形を考える、デザインとはそういうことだ。
以前に予想していたのとは少し違うが、彼はデザイナーとしての道を歩き始めた。
三十人のスタッフがいる開発企画部の中での彼の上司は、組織のトップである部長だった。
部長の下には次長と呼ばれる人がいて、それが五人のチーフデザイナー(社内での正式な役職名は課長か係長だったが、部内では全員が等しくチーフと呼ばれていた)を指揮し、それぞれのチーフの下に数人の一般社員がいるという組織なのだが、なぜか彼だけが部長の直属ということになった。
学歴のせいなのか、吸収合併された工場の出身だからなのか、彼は一人悩んだ。
そしていつも危機感を持って毎日を過ごした。
いつクビを言い渡されるかしれない。
異例な処遇の本当の理由が、くだんの部長が彼の才能に目を付けたからであることなど、当時の彼には知るよしもなかった。
新人デザイナーにはチーフに与えられる業務とは別に、一定のスキルを身に付けるための研修プログラムが準備されていた。
居住環境や材質や力学の応用的な知識の習得を課せられた他の新人デザイナーと違って、彼に与えられたのは人間工学に関する書物だけだった。
彼はそれを通じて、人間の生活に様々な影響を与え続ける道具の重要性を知った。
道具のあるべき姿を考察することに深い興味を覚えた。
当時の日本にまだ一人も存在しなかった、認知工学者が誕生した瞬間だった。
文明とは道具の進化のことを言い、道具を操ることで人は人になった。
道具は使われてこそその本来の使命を果たすものだが、道具の中にも使いやすいものとそうでないものとがある。
目的とする機能が備わっていない道具などの存在は別にして、まったく同等の機能を有する道具ではあっても、その道具の形状のいかんによって、使いやすいだとかそうでないとかは左右されるものだ。
これからの新しく作られる道具には様々な機能が要求されるのは必至だが、複雑な形状であればそれを使う側は混乱してしまうには違いない。
既に実現してしまった機能の改良であれば、前に作られた道具のちょっとした変更だけで、初めてその道具を使う人でも何のフラストレーションも感じることなくその道具を手にするに違いない。
しかし、まったく新しい、今までにない機能を持った道具は次々にあらわれることだろう。
彼は、そうした道具を提供する立場にあるデザイナーに必要なものは、「最小限の前提」と使う側の「推測を利用」したデザインであると結論づけた。
分厚いマニュアルが必要な道具は、彼の定義に従えばそれは悪い道具であり、ある道具の説明会や講習会の開催はそれが使いにくいことを喧伝していることと等価なのだ。
かつて、アインシュタインが「e=Mc2」という簡潔な言葉で、この世界の因果の根本を説明したように、新しいモノをカタチ造る立場のすべてのデザイナーは、極力シンプルな言葉でモノの本質を説明できるべきだ、と訴えた。
そうでなければ、それは悪いデザインであり、使えないモノだと言った。
彼は、世の中のあらゆる道具について批難した。
彼は、周囲のデザイナーに煙たがられる存在になってしまっていた。
そんな彼がある時、いきなり麻雀打ちになってしまった。
麻雀打ちになった経緯にもいろいろとあるのだが、問題にすべきは、認知工学者が麻雀打ちになったそのことにつきる。
認知工学者といい麻雀打ちとはいっても、彼の論文が学会で認められることはなかったし、また麻雀でも彼よりも強い打ち手は巷にゴロゴロとしていた。
認知工学者としての彼のせいで、麻雀打ちとしての彼は悩める毎日を送ることになった。
認知工学者としての彼は何事にも例外を認めたくない立場の人間である。
七対子や国士無双という役の存在が気に入らなかった。
親と南家だけが十八枚ものツモ牌があるのも気に入らなかった。
さらには、ポンやカンによって順番が飛ばされるのも嫌だったし、何かにつけて「頭ハネ」というのも理不尽な気がした。
しかし、そのようなことは常識的な決めごとであるので、渋々でもそれに従わなければ麻雀打ちとしてはやってはいけない。
彼はルールについては、仕方なく皆に従うことにした。
ルールさえ守っていればその他の多くの事は許されるものだ。
認知工学者としての彼は、点棒が気に入らなかった。
百点棒から万点棒まで四種類か五種類の点棒があるが、それらの間には何の相関も見出せない。
認知工学を熟知しているデザイナーがもし点棒をデザインすれば、千点棒は一目見ただけで百点棒十本分の価値があることが誰にでも理解できるような形状にするだろうと思えたし、それと同様に五千点棒も万点棒もデザインされるのが正しいやり方のはずだ。
そして、その相関を一度経験した道具の利用者(この場合は麻雀をする人)にとっては、五百点棒やさらには五万点棒などというものが必要とされる事態となっても、何のちゅうちょもなく自然に新しい道具を使いこなすに違いない。
しかし、実際の彼は点棒をデザインする仕事についているわけでなく、たった今、かかったばかりの親のリーチの一発目の捨て牌に対応しなければいけない立場なので、そんなことを考えていてはいけないのだった。
リーチ宣言した牌がポンされて、後になっていつリーチがかけられたのか誰もが迷うような事態も、認知工学者の彼には捨て牌と副露のやり方に関するデザインがまったくなっていないからだと思えた。
ポンするのにわざわざ他人の捨て牌から牌を持ってくるのが問題なのだから、二枚だけを右端にさらせばいいじゃないかと思った。
いや、それでは同一の牌が続けて切られた時に、前の牌を鳴いたのか後の牌を鳴いたのか判らなくなってしまいそうで、もっと他にうまい解決手法はないものか...。
なんて考えている間に自分のツモ番が廻ってくるので、麻雀打ちとしての彼は焦ってばかりいるのだ。
認知工学者である彼は他の学者がそうであるように一種の教条主義者でもあって、麻雀用語のいくつかにも気に入らないことがあった。
順子(シュンツ)を構成する可能性を持った二枚の牌の呼び名(搭子、辺搭、嵌搭)についての問題や、面子(メンツ)という言葉のちゃんとした定義に関する問題や、振り込むことも麻雀をすることも「打つ」という言葉で一緒くたにしてしまっていることや、同様に「ツモる」「門前(メンゼン)」などといった用語についていつも頭を抱えていた。
麻雀打ちとしての彼にとっては、そんなへ理屈なんてどうでもよく、ただ集中していたいのに、いつでもデザインの何たるかを偉そうに考えている認知工学者の彼は、とても疎ましい存在である。
認知工学者の彼は、デザイナー出身であるためについつい道具に焦点をあてた見方についての問題ばかりが取りざたされてしまったが、実際の彼が抱えている問題はもっと重大のようだ。
それがどういった類いの問題なのかは、不明だ(何だ、そりゃぁ)。