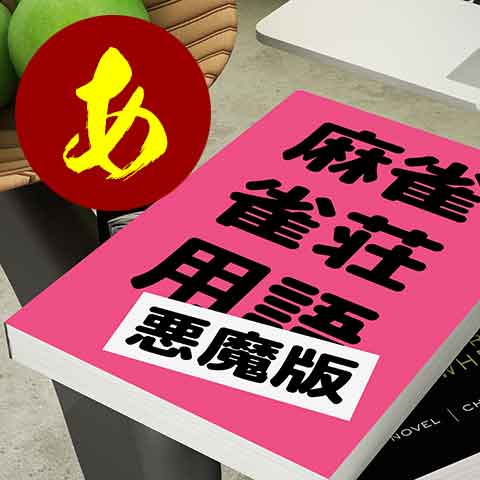あーるしあーる【アールシアール/二十二】和了役や規則
太古の昔、至る所で信仰されたオカルト教義。
今でも日本のどこかの麻雀クラブでは密かに信仰されているはずだが、カタギの衆の目に触れることはなかなかない。
あうと【アウト】雀荘システム
これ以上、自分の財布からお金を出しても取り返せる保証がない場合や、お金を出したくない場合に、常連の客が少しも悪びれることなく、さも当然のように借金を催促すること。
あうとおーばー【アウトオーバー】雀荘システム
ファッション用語では外出する際に重ね着するコートの一種。スポーツ用語では野球で1回に3アウトを超えてしまうこと。もしくは、ドイツで速度制限のない道路がなまった言い方。
さらに、何回も同じ相手に出会うことがあって、それがいつも同級生の大場君である場合に「会うと、大場」。
あおてんじょう【青天井】和了役や規則
麻雀の得点は倍々計算が基本であるが、この倍々計算をどこまで続けることができるかを競うルール。
中国の宮中でこのルールの麻雀が行われる部屋の天井の装飾が、青い色を基調としたデザインであったのでこう呼ばれる。
あか【赤】グッズの呼称
赤ドラ。
偶然性の排除もしくは低減をやかましく口にする競技志向の打ち手から嫌われる赤ドラだが、その実、裏ドラよりも偶然性は小さい。
あか【アカ/赤】雀荘システム
赤字。
普通の計算=クラブに入った時点の持ち金ークラブを出る際の持ち金。
弱者の計算=クラブに入った時点の持ち金ークラブを出る際の持ち金ークラブでの飲食代+クラブにアウトした額。
強者の計算=クラブに入った時点の持ち金ークラブを出る際の持ち金+クラブに居た時間で麻雀以外で稼ぐことができたであろう金額+大勝ちしたために次回には自分と同卓に付くのを嫌がる可能性のあるカモから将来獲得することのできた筈の金額+自分の消費エネルギー。
あがさん【アガサン/あが三】ゲームの進行
オーラスの和了で、ラスから三着に上がったことを言い訳に、せっかくのトップ争いを台無しにした行為をごまかすこと。
最初にこの行為をやったのが「阿賀さん」という人であったのでこう言われるという説もあるが、信ぴょう性は薄い。
あかぼう【赤棒】グッズの呼称
高校時代に「赤坊」と呼ばれる同級生がいたが、彼の名字は「赤崎」だった。
あがらす【アガラス】ゲームの進行
自分で和了らずに、他人に「和了らす」行為。
最初にこの行為をやったのが「阿賀さん」という人であったのでこう言われるという説なんて聞いたことがない。
あがり【アガリ】グッズの呼称
たかだか、お茶を注文する際に、さも自分が「通」であるかのように振る舞うために使う言葉。
あがりぐせ【和了り癖】諺や言い回し
よく和了れるようになるために、あるいはイザという時に和了れないなんてことを避けるために、小さな点数の手であっても和了っておく時のイイワケ。
あがりほうき【和了り放棄】和了役や規則
放棄なんて言うと、自分ですすんで和了る権利を放棄したかのように思われがちだが、実際には和了る権利をはく奪されること。
あがりやめ【アガリやめ/和了り止め】雀荘システム
これ以上、連荘すると、他の三人が卓を離れてしまいそうなので、そうさせないために小さなトップで満足すること。
一般には謙虚な行為と思われているが、実はかなり傲慢なことだ。
因みに「雨上がり」とは語呂が似ているが何の関係もない(と思われる)。
あがりゆうせん【和了り優先/アガリ優先】和了役や規則
誰かが和了ったスグ後でなら、何をやっても咎められないという、麻雀の大原則。
大阪有線や回遊船とは一部の語呂が似ているが何の関係もない(と思われる)。
あがりれんちゃん【和了り連荘】和了役や規則
荘家で聴牌していても連荘しなくても良い、という、トップ目の荘家に優位なルール。
逆に、「リードは守るものでなく、広げるものだ」を信条とする八崎やアタキのような傲慢な打ち手にとっては、いささかやりにくい規則でもある。
あくうかん【亜空間】戦術戦略理論
空間に近いこと。もしくは、空間に準ずること。たまには空間であること。
転じて、いつまで経っても空間に届かないこと。
あずかり【預り】雀荘システム
(1)金品や高価な物品を預かること。
(2)預かった証拠に渡す書き付け。預かり証。
(3)勝敗が長びくなどして決まらない場合、勝ち負けを決めないでおくこと。
(4)平安時代の官職。御書所・画所などに置かれ、その事務をつかさどるもの。
(5)人の世話や家などの管理を委任されている人。
あたま【雀頭】基本的な用語
どの牌を切るべきか悩み過ぎて頭が痛くなった時には、雀頭を決めつけてしまうとそれ以上、頭は痛くならない。
あたまはね【頭ハネ/頭跳ね】和了役や規則
頭が跳ねるわけでもなく、頭が跳ねられるわけでもなく、頭に跳ねられもしないのに、なぜ「頭跳ね」なのか。
この場合の頭とは実は「頭」のことではなく、「あんた、まぁ」の変化形ではないか、というような説は聞いたことがない。今、思い付いただけだ。
あたり【当たり】ゲームの進行
囲碁の場合の「アタリ」は、もう一歩で相手の石を取ることができる状態を言うが、麻雀の場合にはもう完了してしまっている。
本来であれば、「この牌を切ろうと思うんですけど」と言いつつ、自分が捨てるつもりの牌を他の三人に見せ、誰かが「アタリ」と口にしたらその牌を捨てなくとも良い、というようなルールの時にしか使えない言葉だと思う。思う。強く思う。故に我在り。
あとづけ【後付け】和了役や規則
物事の後につける心づくし。
あとひっかけ【後引っ掛け】戦術戦略理論
後ろ足で引っ掛けること、もしくは後ろ向きで引っ掛けること。
たまに、後ろの人を引っ掛ける場合にも使う。
ありあり【アリアリ/有り有り】和了役や規則
何でも認められているルール。
先自摸アリ、イカサマアリ、共謀アリ。
反意語は「ナシナシ」。
ありす【アリス】和了役や規則
「大変だ、大変だ、遅れてしまう」と何やら急いでいる時計うさぎの後を追って、アリスが入った洞くつの中には、当然のように、いろんな麻雀打ちが様々なルールで麻雀をやっていましたとさ。
あわせうち【合わせ打ち】戦術戦略理論
上家、もしくは下家と同じタイミングで、捨て牌を行うこと。
上家に合わせ打ちする場合には、先自摸し瞬時に牌を切らなければならないので、かなりの習熟を必要とされる。
下家に合わせ打ちする場合には、下家を待たせてイライラさせるまでタイミングをはからなければならないので、ズ太い神経が必要である。
あんかん【暗槓】基本的な用語
初心者に質問された。
「アンカンはあるのに、アンポンやアンチイが無いのは何故か。逆に、アンカンだけあるのは何故か」
暗刻や暗順のことでなく、行為によって右にさらすポンやチイのことだ。
うざい奴だったので適当に放っておいたが、なかなか進歩的な疑問ではある。
アンポンやアンチイがあれば、メンチン聴牌時に(手牌は狭くなるが)迷うこともなくなるだろう。
あんぱい【安牌】基本的な用語
一番、得点が低くなる和了り牌。安い牌。
いーしゃんてん【一向聴】ゲームの進行
一つの向聴(しゃんてん)。
聴牌るためにはいくつかの必要牌の選択肢があるが、色々とある中の一つ。
いーしゃんてんじごく【一向聴地獄】ゲームの進行
一つしかない向聴(しゃんてん)が地獄の状態(意味不明)。
いーちゃん【一荘】基本的な用語
一つの荘。
いかさま【イカサマ】戦術戦略理論
いかにもそのものらしい、偽者、まがいもの。
つまり和了ってもいないのに和了ったように見せかけたり、六つしか対子がないのに七対子だと思わせたり、自分の正規のツモ牌でもないのにツモったり、嘘の申告をしたりすること。
という定義なので、「トーシ(ローズ)」や「積み込み」は、真の意味のいかさまとは言えない。
いちなき【一鳴き】戦術戦略理論
配牌を開いてみたら、クズ手で、とても勝負に参戦できないなと思ったら、とりあえず、何の意味もない牌をポンしておくことによって、他の三人の手の進行を遅らせるために利用する仕掛けの一つ。
成功しなくても、アタキの責任じゃない。
いっしょく【一色】基本的な用語
赤牌なんて入っている場合には正式な一色とは言えない。
考えてみると、萬子も数字部分と「萬」の部分は色が違うので、一色とは言えない。 や
や や
や や
や や
や も明らかに一色ではない。
も明らかに一色ではない。
同じく


 もダメだ。
もダメだ。
はっ、本当に一色なのは だけじゃん。
だけじゃん。
いっぱつ【一発】和了役や規則
「発」は助数詞なので、本来、弾丸やオナラを数える時に使うものだ。一発、二発と。
しかし、リーチに二発や三発はありえないので、「リーチ一発」という使い方は間違っていると思われる。
いやいや、よく考えてみると、「一発変換」だとか「これで、男性心理が一発で理解る」だとかもよく使われるので、この「一発」は「本来ならば何度かの手間が必要だけれども、たった一回で」というような意味を持っていると考えられ、ここまでくると、助数詞の「発」ではなく、「一発」という一つの単語であるような気がしてきた。
アタキは 100% 理工系の人間なので、この解釈には自信がある筈もないが、誰か本当の所を教えてほしい。
いっぱつけし【一発消し】戦術戦略理論
他者のリーチ一発を無効にするために、一発で何らかの行為を起こすこと。
いろ【色】基本的な用語
光による視神経の刺激が脳の視覚中枢に伝えられて生ずる感覚。色相、明度、彩度によって決まる。
麻雀における色相はスートの種類、明度とは端に近いか否か(5が一番明度が高く、1と9の明度が低い)、彩度は場に捨てられている枚数のことを言う。
ただし、ドラやドラの近辺は光り輝く場合もある。
いんぱち【インパチ】和了役や規則
そこそこに大きな点数であって、普通の麻雀だったら、これだけで勝負の趨勢が決まることもある。
だけど、サンマやワレ目が身に染み付いた打ち手は、ただの「親の跳ね満」という認識しかしない。
うかせうち【浮かせ打ち】戦術戦略理論
標的にしている相手をオーラス直前まで、原点より浮かせておいて、最後に沈める戦法。
「いやぁ、惜しかったですね」「もう一息でトップでしたね、次は頑張りましょう」
立派なバイニンの言葉である。
うきしずみ【浮き沈み】基本的な用語
着順に重きを置くか、浮き沈みに重きを置くかは戦略を立てる際の重要な分岐点である。と先人が言ったのか言わないのか知らないが、実の所、どちらも結果論であって、せいぜいがラス前あたりから意識する事柄に過ぎない。
うたう【歌う】戦術戦略理論
「ポン」や「リーチ」の発声の際、メロディに乗せて声を出すこと。
四人全員が歌う卓のことを「歌会(うたかい)」と言い、他者の歌を批評しあったり、深く味わったりすることがある。
歌うことを専門にしている打ち手は「歌手」や「歌い手」と呼ばれ、その年にもっとも優れた歌い手は、大晦日のNHKの番組に出場できる可能性もある。
うちすじ【打ち筋】基本的な用語
筋を打つこと。
打ち筋のしっかりした打ち手は、147と決めたら、最後まで147の牌しか打たない。
中でも258ばかりの打ち筋の場合は、「流し断ヤオ」という振り切り役との両天秤を謀られることがある。
うつ【打つ】基本的な用語
ギャンブルをすること。「博打を打つ」「碁を打つ」「麻雀を打つ」たまに「パチンコを打つ」。
しかし「将棋」や「花札」や「宝くじ」や「競馬」を「打つ」とは言わない。
もちろん、健康麻雀はギャンブルではないので、「打つ」とは言わない。
うら【ウラ/裏】和了役や規則
牌の裏側。
うらおもて【裏表】ゲームの進行
牌の裏側と表側。
うんしちわざさん【運七技三】諺や言い回し
麻雀の勝敗を決するものは、「本人の雀力」「経験」「センス」「座る場所」「上家の腕」「その日の体調」「お腹の空き具合」「雀荘の方位」「財布の中身の余裕」「今は本職の就業時間内か否か」の10項目であるが、この内の何が「運」でどれが「技」なんだろうか。誰か教えてほしい。
えあわせ【絵合わせ】基本的な用語
麻雀の本質。
えーとっぷ【Aトップ】和了役や規則
AトップだろうがBトップだろうが、もしもクラブが徴収するゲーム料金が常に一定であればこんな呼称は生まれなかった。
マルAの時や、ゲンツー(浮きの2着がいる際のBトップ)の時には徴収料金が微妙に違った筈なのだ。
う~ん、記憶が、記憶が、さだかじゃない。
えらー【エラー】雀荘システム
失策。特に野球で,野手の捕球や送球の失敗により,アウトにできるはずの走者を生かすこと。
転じて麻雀では、一発消しできるにも関わらず副露しないことや、カンできるのにしなかった場合、あるいは自分の和了点の申告を大目に言って、それが発覚したような時のことを指す
おいかけりーち【追いかけリーチ/追い掛け立直】戦術戦略理論
元々は「追い風リーチ」と言った。
既にトップが確定の優位な状況でダマ聴してたら、何をトチ狂ったか苦しそうな形でリーチをかけてくる奴がいた際には、ツモ切りで続けてリーチすると、一発で和了れることが多いのでそう呼ばれた。
おうごんのいーしゃんてん【黄金の一向聴】人物/その他
手を進めていく内に、三色同順と一気通貫の両天秤にかけられる一向聴形になってしまい、「おお、こんな一向聴になった」と言われたのが始まり。
「おお、こんな一向聴」が「黄金の一向聴」に転じた。
おうごんぱい【黄金牌】グッズの呼称
牌のあらゆる部分が黄金で出来ている(完璧な)黄金牌で囲んでいる際に感じたのだが、はっきり言って、何が書いてあるのか判らない。
だから盲牌でその牌が何であるのかを確かめていたが、問題は捨て牌であって、他人の捨て牌を盲牌するなんて毎度やれるものじゃないので、全員が捨て牌時にその牌を発声するというルールになった。
しかし、自分の河ならともかく、他人の河の一度言われた牌を完璧に記憶するなんて、なかなか困難なことで、そのあたりは勘に頼っての進行となってしまった。
こうした事実はあまり知られていない。
おうてびしゃ【王手飛車】和了役や規則
和了牌によって、跳ね満と倍満クラスの聴牌時には「王手飛車」と呼んでもよいが、ゴンニとザンクくらいの手なら「桂馬と銀取り」あたりが相応しい。まして、1000点1300点(平和と断ヤオ)なら「目クソ耳クソ」で充分。
おーぷん【オープン】和了役や規則
卓上だけでなく、卓の周囲も敵だらけという状況にあっては、自分の手牌を立てていても無意味だ。
そこで「オープン」である。どうせ聴牌はバレているので、自分でツモるしかないわけで、あれっ、これって、何かの漫画で見たことあるぞ。
はい、はっぽうやぶれのタケオですな。
「どうせこっちの手は通されとるし、和了り目はなかとじゃ。国士ば狙うちゃる!」
おーらす【オーラス】ゲームの進行
延々とどこまでも続けても構わないのだけれど、そこはそれ、一応の区切りみたいなのがあると、何となくしっくりするので、設けてある一つのタイミング。
オールラストの略ではあるが、これで本当にラストになることはあまり無く、次のゲームへの繋ぎであることが多い。
ある研究によると、オーラスがその日の最終局になる確率はそうとはならない確率の25%よりも小さい。
おーるまいてぃ【オールマイティ】和了役や規則
何にでもなる牌。
だけど点棒やサイコロやお金にはならない。
おか【オカ/岡】和了役や規則
自分が慣れ親しんだオカとあまりに差が開き過ぎるオカ(例えば 10000点持ちの 30000点返し)で勝負をすると、どういう展開を想定して勝負を廻すべきなのかに高度な判断を要求される。
それがうまくできない打ち手はオロオロとしてしまい「オカに上がった河童」と呼ばれる。
おかわり【お代わり】雀荘システム
普通の状態、もしくは普通の打ち手であれば、一杯でお腹いっぱいになるのに、なぜか空腹感がいやされずに、ついついやってしまうお代り。
バイトメンバーは居候ではないが、三杯目をそっと出すとも言われる。
おきゃくさん【お客さん、いらっしゃい!】諺や言い回し
クラブにお金を落としてくれる人々。
クラブからお金を巻き上げる人のことをこう呼ぶのは間違い。
おたかぜ【オタ風/客風】和了役や規則
平和の雀頭にはなるくせに、暗刻ると、自風と同じ点数になるのは納得いきません。
おなてん【オナ聴】ゲームの進行
同じテンパイ、の意。
さっきの局とオナ聴、昨日の親の手とオナ聴、一週間前に隣の卓で誰かがリーチした手とオナ聴、今まで世界中のどこかで誰かが聴牌した時とオナ聴。
おばけ【お化け】戦術戦略理論
さっきまで国士無双狙いだったのに、いつのまにか七対子に化けてしまった。
さっきまで四暗刻を狙っていたのに、いつのまにか七対子に化けてしまった。
さっきまで純全帯么に走るつもりだったのに、いつのまにか七対子に化けてしまった。
おも【オモ】和了役や規則
最も発生頻度の高い倍満は、「リーヅモ、チイトイ、オモオモ、ウラウラ」。
おやぎめ【親決め】ゲームの進行
俺的には何と言うか、いきなり親を決める、っては、直接的過ぎてあまり面白くないようにも思うんだよね。
例えば目の前のコーヒーカップを描くにしても、いきなりそのカップの縁取りを描くんじゃなくって、回りのテーブルやその上の小物や、つまりはコーヒーカップ以外のものを描写していった結果として、カップがキャンバスに浮かび上がってくる、みたいな、そうした方法も素敵なんじゃないかと。
そうすることで、コーヒーカップと他の物との相違性が明確になって、本質、という点では優れているのかもしれないね。
つまりは、いきなり親を決めるんじゃなくって、子を一人一人決めていって、三人が決まってしまったら残りの一人が実は親なんだ、というアプローチだって誰も否定できないと思うんだよね。
おやこうこう【親孝行】人物/その他
親の手をアシストする、親のツモ回数を増やす、親のキー牌をプレゼントする、親以外の他の打ち手を牽制するようなリーチをかける、親からのロン牌を見逃す、など。
おやっかぶり【親っかぶり/親っ被り】ゲームの進行
親がかぶること、もしくは親がかぶるもの、時には親がかぶった瞬間。
被る(もしくは冠る)わけだから、害を被るとか罪を被るの「がぶる」に違いない。
親であることの罪とは一体何だろう。考えてみると面白そうなので放言ネタにとっておこう。
おやばん【親番】和了役や規則
親がツモる順番。
おり【オリ/降り】戦術戦略理論
切れない牌があって処分できそうにない、手が悪い(低い、もしくは遅い)、持ち点が多く勝負に参戦する必要がない、熾烈な争いとは無縁な状態に置かれてしまっている、今日は充分に勝ったので取りあえずケンだ、普通に手を進めるよりも振り切り(流し満貫)の方が狙いやすそうだ、等の目論みがあってオリる。
よく考えてみるとオリてはいない。
おんらいんまーじゃん【オンライン麻雀】基本的な用語
全員がある一本の線上で囲む麻雀。
誰か一人でも、その線を外れるとオフライン麻雀と呼ばれる。
おんれーと【オンレート】和了役や規則
幽霊とは無関係。